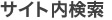‘書籍案内’ 一覧
新 臨床神経眼科学(増補改訂版)
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho038.htm新 臨床神経眼科学(増補改訂版
 |
あれから3年、さらにUp to dateな内容を盛り込み、さらに神経眼科の最先端へ
品切れ |
|||||||
執筆者(五十音順)
池田誠宏,池田尚弘,内海隆生,片野拓哉,神野早苗,木村亜紀子,木村直樹,栗本拓治,来栖昭博,鈴木温,田野良太郎,寺田木綿子,内藤哲行,西崎順也, 西村雅史,秦真実,平島育美,藤井雅彦,古河雅也,平島育美,藤井雅彦,古河雅也,保科幸次,三村治,山縣祥隆,山田元子(以上,兵庫医科大学)
安積 淳,石橋一樹,井上正則,金森章泰,楠原仙太郎,石橋和子,関谷善文,中村誠,根木昭,前田秀高(以上,神戸大学)
絵野亜矢子(大阪バイオサイエンス研 究所)
岩崎嘉秀(芦屋市立病院)
野村耕治,山田裕子(以上,兵庫県立こども病院)
三反田智博(宝塚市立病院)
波田順次(神鋼病院)
山本恭三(京都 府立医科大学)
本書が上梓されてから3年が経過しましたが、その間にもすでに画像診断法や遺伝子診断などいくつかの分野で新しい知見が得られ、編者としては最新の情報を 伝えきれていないことにもどかしさを感じていました。本書は当初から、最新の神経眼科学の知識を読者にお伝えすることを至上命題としていましたので、今回 版を重ねるのを機会に、部分的ではありますが改訂を行うことになりました
今回の改訂では、初版発行後ご指摘いただいた誤りや誤植の訂正以外に、「外転神経麻痺」の項をすべて書き直すなど、全部で32項目に関して全面的あるい は部分的に加筆修正を行っています。図も不鮮明なものは鮮明なものにかえ、文献も可能であれば最新のものを引用しています。また、最後の「これからの神経 眼科」の章には、とくに進歩の著しい画像診断法として「Fiber tracking」の項を追加しています。
この増補改訂版が神経眼科学の標準的な成書となり、読者の診療と研究に役立てれば編者の大いなる幸いです。
(序文より)
内容目次
| I | 神経眼科における診察法・検査法 | ||
| II | 視路の異常 | ||
| 1.視神経障害/2.視交叉およびその近傍の病変/3.上位視路の病変 | |||
| III | 眼球運動の異常 | ||
| 1.核上性眼球運動障害/2.核および核下性眼球運動障害/3.神経筋接合部障害/4.外眼筋および周囲組織の異常/5.眼振および異常眼球運動 | |||
| IV | 瞳孔・調節・輻湊機能の異常 | ||
| 1.瞳孔・調節機能の異常/2.輻湊・開散機能の異常 | |||
| V | 眼窩・眼瞼の異常 | ||
| 1.眼窩の異常/2.眼瞼の異常 | |||
| VI | その他 | ||
| 1.心因性反応/2.全身疾患と神経眼科/3.網膜疾患の接点/4.緑内障との接点/5.各種検査 | |||
| VII | これからの神経眼科 | ||
| 1.視神経移植と再生/2.遺伝子診断と治療/3.実験的視神経炎/4.視神経症の新しい治療法の試み/5.膝状体外視覚系/6.固視微動の解析 /7.Functional MRI /8.Fiber tracking | |||
眼科学 ■疾患とその基礎■(改訂版)
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho039.htm眼科学 ■疾患とその基礎■(改訂版)
 |
考える診療のために! 眼科医,研修医,学生,眼科学に携わるすべての人々必読の書!
|
|||||||
最近の科学の進歩は実にめざましい。「十年一昔」などという言葉はすでに死語となり、「五年一昔」とか「三年一昔」と言われるほどに進歩の速度を早めてい る。このような高速進歩を可能にしたのは「ブラックボックスの概念」ではないかと考えられる。すなわち、先人が苦労して獲得した原理・原則をブラックボッ クスの中に閉じこめ、「何故そうなったのか」についてもう一度苦労して理解し直すのではなく、「どうすればどうなるのか」のみを追求することが、進歩に取 り残されない最良の方法であるとされているからである。最近の医学書にもこの考えが取り入れられ、「こうすればこうなる」といういわゆる「how-toも の」が多くなり、「何故先人がそう考えたのか」について書くと、進歩についていけなくなるのではないかという不安さえ与えかねない風潮になっている。
本書では疾患の診断と治療について「現時点における」と限定した上で、最も正しいと思われる方法を述べるとともに、その疾患についての基礎知識をもとに「何故そう診断したのか」や「何故そのような治療法をとったのか」について解説している。
本書が、読者諸氏の日常診療において、ブラックボックス方式の丸暗記ではない、考える診療が実現されるなら望外の幸せである。
(序文より)
内容目次
| I | 総論 | ||
| II | 眼科診療室にて | ||
| III | 眼瞼 | ||
| IV | 涙器(涙腺,涙道) | ||
| V | 結膜 | ||
| VI | 角膜 | ||
| VII | 強膜 | ||
| VIII | ぶどう膜 | ||
| IX | 水晶体 | ||
| X | 網膜硝子体 | ||
| XI | 視路,瞳孔,眼球運動 | ||
| XII | 眼窩 | ||
| XIII | 緑内障 | ||
| XIV | 斜視,弱視 | ||
| XV | 屈折・調節異常 | ||
| XVI | 光覚・色覚の異常 | ||
| XVII | 全身疾患と眼 | ||
| XVIII | 眼のプライマリーケア | ||
| XIX | 眼治療学総論 | ||
| XX | 付録 | ||
| A.眼科略語集/B.眼科関連法律(法令)/C.リハビリテーション/D.主な眼科雑誌の紹介 | |||
コンタクトレンズの正しい使い方-効果的に/安全に/快適に-
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho040.htmコンタクトレンズの正しい使い方-効果的に/安全に/快適に-
 |
|
|||||||
現在、国内におけるコンタクトレンズユーザーは約1,300万人をこえており、これは国民の10人に1人がコンタクトレンズを使用しているということにな ります。わが国ではじめてコンタクトレンズが使用されるようになってから約50年が過ぎました。この間に各メーカーの研究、開発、技術の向上により、レン ズ材質、レンズデザインの改良が進み、現在ではじつに豊富な種類のレンズが発売されています。しかし、どんなにすぐれたコンタクトレンズでも、目にとって は異物です。適切な処方、正しい使用、定期検査などが行われなければトラブルが生じ、ときには失明に至る場合もあります。今後、さらに、コンタクトレンズ の使用を希望する人は老若男女を問わず増加することは明らかですが、コンタクトレンズの普及に伴い、コンタクトレンズに対する誤った認識が広まることも懸 念されます。そこで、少しでも多くの方々に、コンタクトレンズは医療用具であり、医師による処方、指導、管理が必要であることをご理解いただけるよう、コ ンタクトレンズを効果的に安全にかつ快適に使用するためのポイントを本書で述べようと思います。
ところで、現代の医療現場においては、”インフォームドコンセント”が欠かせないものとなっています。
当然コンタクトレンズ診療においても、医師と患者との信頼関係を築くために”インフォームドコンセント”は重要で、コンタクトレンズの選択、処方にとどまらず、レンズケア、コンタクトレンズ処方後のクレーム、コンタクトレンズ装用に伴う合併症など、コンタクトレンズに関するあらゆる点で必要となります。ま た、コンタクトレンズ量販店の進出や安売り広告、他科の医師や無資格者によるコンタクトレンズ処方、インターネットや通信販売などの医師の診察、検査を介 さないコンタクトレンズの購入といったような、時代の流れとともに多様化するコンタクトレンズ問題、これに伴って生じたトラブルへの対応についても十分な 説明をしなければなりません。しかし、実際には、患者に十分納得してもらうためにどのような説明をすればよいか苦慮することが多いようです。そこで、本書 は、日々の外来において患者からよく質問される内容を取り上げ、むずかしい表現を使用せず、なるべくわかりやすくQ&A方式で解説しました。忙しい外来の限られた時間のなかでスムーズなインフォームドコンセントが行われるために、少しでも役に立つことができれば幸いです。
(序より)
内容
| ●56項目のQ&A | |||
| ●10項目の付録 | |||
| ●カラー写真・図など多数 |
眼科症候群辞典<増補改訂版>
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho041.htm眼科症候群辞典<増補改訂版>
 |
|
|||||||
眼科症候群辞典」は、多くの眼科研修医から眼科専門医制度認定医、さらにはこれらの人たちを教育する立場にある教室のベテランの医師たちにも、至便の書としてたえず傍らに携えられてきた。
本書は眼科に関連した症候群の、単なる眼症状の羅列ではなく、疾患自体の概要や全身症状について簡潔に述べてあり、また一部には原因、治療、予後などの解説 が加えられている。比較的珍しい名前の症候群や疾患のみならず、著名な疾患の場合でも、その概要や眼症状などを知ろうとして文献や教科書を探索すると、意 外に手間のかかるものである。ことに、日常外来の最中に他科から診察を依頼された疾患の眼合併症のような場合、図書館にかけこんで調べる暇はない。
あ らたに追補したのは95項目で、Medlineや医学中央雑誌から拾いあげた。執筆に当たっては、 眼科系の雑誌や教科書とともに、内科系の症候群辞典も参考にさせていただいた。本書が第1版発行の時と同じように、多くの眼科医に携えられることを期待す る。
<改訂版への序文より>
本書の特色
| 1 | 眼科領域で扱われている症候群をアルファベット順にすべて収録(総509症候群) | ||
| 2 | 各症候群の「眼所見」については、重点的に解説 | ||
| 3 | 他科の実地医家にも十分役立つよう歴史・由来・全身症状・治療法など、広範な解説 | ||
| 4 | 各症候群に関する最新の、入手可能な文献をも収載 | ||
視能訓練士-スペシャリストへの道
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho042.htm視能訓練士-スペシャリストへの道
国家試験問題集・解答と解説 平成9~11年版
- その他の『視能訓練士-スペシャリストへの道』はこちら
 |
わかりやすい2色刷 詳細な解説 平成9~11年の過去問題を分野別に収録 豊富な練習問題 受験生必携の書!
|
|||||||
わが国の視能訓練士の歴史は浅いといわれていますが、日本眼科学会視能訓練士認定試験(第1回)が行われたのが1974年、視能訓練士法が成立したのはそ れ以前の1971年であり、もう既に30年を経ております。この年に視能訓練士国家試験が施行されて以後、年々、資格者が増えて、今では4,267人を数 えるに至っております
しかし、一通り学習しただけでは、国家試験問題もうまく解答できないことがあります。
そこで今回、日本弱視斜視学会、日本視能矯正学会などで活躍中の新進気鋭の先生方、視能訓練士の方々にお願いしまして、各項目ごとに簡潔な解説をして、視 能矯正学を違った角度から理解を深めるとともに、既出問題や類似問題に十分対応できるよう解答と解説を加えていただきました。本書は単に国家試験の対策書 だけでなく、幅広く応用の利く知識を身につけてスペシャリストとして活躍される事を期待するための書であります。
(序文より)
内容目次(執筆者)
| I | 発達臨床心理学 | ||
| 向野和雄(北里大学医療衛生学部 視覚機能療法学・教授)/山下牧子(東京医科歯科大学医学部) | |||
| II | 視器の解剖と生理 | ||
| 母坪雅子(札幌きい眼科・副院長) /関谷善文(神戸大学大学院 器官治療医学・講師) /藤山由紀子(北里大学医療衛生学部 視覚機能療法学・助教授) | |||
| III | 眼の機能 | ||
| 橋本禎子(福島県立医科大学医学部 眼科・講師) /木井利明(札幌きい眼科・院長) /平井淑江(名古屋大学医学部 眼科) | |||
| IV | 生理光学 | ||
| 魚里 博(北里大学医療衛生学部 生理光学・教授) /鵜飼一彦(日本福祉大学情報社会科学部・教授) /小島ともゑ(大阪医専 視能訓練学科) | |||
| V | 眼科疾患 | ||
| 溝部惠子(済生会京都府病院 眼科・部長) /菅澤 淳(大阪医科大学 眼科・助教授) | |||
| VI | 眼薬理 | ||
| 関谷善文(神戸大学大学院 器官治療医学・講師) /松本富美子(近畿大学医学部堺病院眼科) | |||
| VII | 神経眼科 | ||
| 山縣祥隆(兵庫医科大学医学部 眼科・助教授) /調 広子(神戸大学大学院 器官治療医学) | |||
| VIII | 視能矯正-基礎編 | ||
| 長谷部 聡(岡山大学医学部 眼科・講師) /内海 隆(大阪医科大学 眼科) /瀧畑能子(滋賀県立小児保健医療センター 眼科) /新井紀子(川崎医科大学 眼科) /金谷まり子(総合新川橋病院 眼科 視能矯正室) | |||
| IX | 視能矯正-各論 | ||
| 木村 久(川崎医科大学 眼科・助教授) /矢ヶ崎悌司(眼科やがさき医院・院長) /野村耕治(兵庫県立こども病院眼科) /久保喜美(国立大阪病院附属視能訓練学院) /濱村美恵子(大阪医科大学 眼科) | |||
| X | 眼科検査と視覚補助具 | ||
| 佐藤美保(名古屋大学医学部 眼科・講師)/佐々本研二(京都市立病院 眼科)/石田加代子(都立心身障害者福祉センター 身体障害相談課視聴覚言語判定係) | |||
| ※以上 10の分野について各章それぞれ過去の問題、解答と解説を収録 | |||
<改訂版>眼鏡
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho043.htm<改訂版>眼鏡
 |
残りわずか!! |
|||||||
ICG螢光眼底造影マニュアル
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho044.htmICG螢光眼底造影マニュアル
 |
インドシアニングリーン(ICG)螢光造影所見の読影に最適の参考書!
品切れ |
|||||||
インドシアニングリーン螢光眼底造影法は、この数年来、国の内外を問わず眼科関連の学会や学術誌を賑わしており、今や脈絡膜造影法として眼底疾患の診断に関して不動の地位を築くまでになっている。
本法によりもたらされた新知見は膨大で、それによる恩恵ははかりしれない。診断方法の急速な発展の陰には、ビデオICG螢光造影装置、SLO、デジタル高解像度赤外螢光眼底造影など、最新のコンピュータ技術をとり入れた造影器機の進歩も見逃せない。
このような現状にありながら、インドシアニングリーン螢光眼底造影法の原理から臨床まで一貫して、系統的に懇切丁寧に書かれた解説書がなく、撮影が煩雑で、読影がむずかしいといった誤った認識が、普遍的な検査法としての定着を妨げている。
そこで、これからICG螢光造影をはじめる人を対象にして、臨床の場ですぐに役に立つ実践的な知識を集約したのが本書である。実践的であることを主目的と し、撮影方法のイロハから、主な疾患の造影所見までを見開きで簡潔にまとめた。とくに疾患の部分は、ICG螢光所見を前面に配置して所見がすぐに比較でき るようにした。また、読影の参考になるように、「コメント」の項を設けて、ICG所見に関する著者の考えを記載した。
(序文より)
内容目次
| はじめに-どうして、この本を出版することになったか? | |||
| ICG螢光造影が歩んできた道 | |||
| I | ICG螢光眼底造影を理解するには | ||
| 1.造影剤(ICG色素)の特徴/2. 種々のICG螢光眼底造影装置をいかに使いわけるか-撮影装置購入の注意点と撮影方法の実際-/3. コンピュータの応用 | |||
| II | ICG螢光造影の読影に必要な基礎的知識 | ||
| 1.眼底の構造と網脈絡膜循環/2.ICG螢光造影(IA)とフルオレセイン螢光造影(FA)とどこが違うか? | |||
| III | ICG螢光眼底造影所見をどう読むか | ||
| 1.正常眼の網脈絡膜造影所見-各種眼底カメラの正常所見と比較-/2.虹彩および結膜血管> | |||
| IV | ICG螢光眼底造影の臨床 | ||
| 1.実際の応用法と主な異常所見/2.脈絡膜新生血管/3.漿液性網膜剥離/4.眼球外傷に伴う脈絡膜症/5.脈絡膜腫瘍/6.網脈絡膜変性疾患/7.網膜血管病 | |||
網膜静脈閉塞症
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho045.htm網膜静脈閉塞症
 |
眼科疾患の中で全身疾患との関連が深く、かつ症例の多い網膜静脈閉塞症についてのわが国ではじめての単行本!
|
|||||||
眼科疾患には角膜疾患、白内障、緑内障、黄斑疾患などの眼科特有の疾患がありますが、全身疾患との 関連が深く、かつ症例の多い疾患に糖尿病網膜症と網膜静脈閉塞症があります。糖尿病網膜症の著書は多 数刊行されていますが、網膜静脈閉塞症については単独の著書は見あたりません。
日常診療において治療する機会の多い網膜静脈閉塞症には、中心静脈閉塞症、分枝静脈閉塞症、半側 中心静脈閉塞症があります。その発症原因には、全身因子としての多くの背景疾患や、局所因子としての網 膜組織の多彩な病変があります。同じような症例でも、さまざまな経過をたどります。
著者は過去35年間に約4,000例をこえる静脈閉塞症の治療を行ってきました。治療の折にふれ文献を調 べているうちに、網膜静脈閉塞症には実に多くの事柄が関連していることを学んできました。本書を執筆し た動機は、一人の眼科医が4,000例以上の網膜静脈閉塞症を経験し、3,000例をこえる光凝固治療を施行 する機会はないのではないかと思い、自験例を含めて網膜静脈閉塞症に随伴する多彩な事柄をまとめて記 載し、網膜静脈閉塞症を理解していただくことは、これから学ぶ諸先生のお役に立つのではないかと考えた ためです。
(序文より)
内容目次
| I | 疫学・統計 | ||
| 1.疫学/2.統計 | |||
| II | 発生機序と病理 | ||
| 1.CRVOの発生機序と病理/2.BRVOの発生機序と病理/3.BRVOと動静脈交叉 | |||
| III | 分類 | ||
| 1.CRVOの分類/2.BRVOの分類/3.Hemi-CRVO(半側網膜中心静脈閉塞症) | |||
| IV | 自然経過 | ||
| 1.CRVOの自然経過/2.BRVOの自然経過 | |||
| V | 臨床所見 | ||
| 1.眼血流動態/2.血液/3.軟性白斑/4.BRVOと大きな血管瘤・網膜細動脈瘤/5.硝子体/6.BRVOと網膜裂孔/7.BRVOと滲出性網膜剥離/8.緑内障 | |||
| VI | 合併症 | ||
| 1.CRVOと毛様網膜動脈閉塞/2.頸動脈海綿静脈洞瘻(CCF)/3.CRVOとoptociliary vein/4.合併症 | |||
| VII | 検査 | ||
| 1.BRVOと屈折/2.CRVOと瞳孔/3.視野/4.ERG・多局所網膜電図・EOG・パターンVECPとBRVO/5.CRVOとICG(インドシアニングリーン螢光眼底造影)/6.網膜厚解析装置(RTA)、光干渉断層計(OCT)/7.BRVOと血液眼柵 | |||
| VIII | 治療 | ||
| 1.薬物治療/2.高気圧酸素療法・星状神経節ブロック/3.光凝固治療/4.硝子体手術 | |||
視能訓練士-スペシャリストへの道<2>
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho046-1.htm視能訓練士-スペシャリストへの道<2>
国家試験問題集・解答と解説 平成12~14年版
- その他の『視能訓練士-スペシャリストへの道』はこちら
 |
わかりやすい2色刷 詳細な解説 平成12~14年の過去問題を分野別に収録 受験生必携の書!
|
|||||||
視能訓練士法が1971年に成立し、第1回の視能訓練士国家試験が施行されてから30余年になります。視能訓練士の有資格者が年々増えて昨年で4,943 人となり、本書の第1版の出たときよりも600人以上増加しています。これらの多くの方々が第1版を見て役に立ったとご好評を頂きました。
視能訓練士養成施設も全国で大学4校、専門学校14校と18校を数え、前回よりも4校増えています。それぞれの養成施設を卒業して、国家試験に合格して一人前の視能訓練士として活躍される事になります。
しかし、スペシャリストの道は奥深く、学校を出て日常臨床の場で役立つには、さらに実地を踏まえての勉強や経験が必要になります。
今回の平成12~14年版においても、日本弱視斜視学会、日本視能矯正学会などで活躍されている先生方、視能訓練士の方々にご協力を頂いて、各問題ごとに簡単な解説を加えて頂きました。
第1版と同じような問題でも、その説明には違った切り口から解説されており、理解を深めることができます。本書は単に国家試験の解説書ではなく、幅広く応用の利く知識を身につけてスペシャリストとしての道を歩んで頂くことを期待するための書であります。
(序文より)
内容目次(執筆者)
| I | 発達臨床心理学 | ||
| 向野和雄(北里大学医療衛生学部 視覚機能療法学・教授)/山下牧子(東京医科歯科大学医学部 眼科) | |||
| II | 視器の解剖と生理 | ||
| 母坪雅子(札幌きい眼科・副院長)/関谷善文(関谷眼科クリニック・院長) | |||
| III | 眼の機能 | ||
| 横山 連(大阪市立総合医療センター 小児科・院長)/平井淑江(愛知淑徳大学 教養教育センター) | |||
| IV | 生理光学 | ||
| 内川義和(九州保健福祉大学 保健科学部 視機能療法学科) /鵜飼一彦(早稲田大学理工学部・教授)/小島ともゑ(大阪医専ツ黴視能訓練学科) | |||
| V | 眼科疾患 | ||
| 溝部惠子(済生会京都府病院ツ黴眼科・部長) /菅澤 淳(大阪医科大学 眼科・助教授) | |||
| VI | 眼薬理 | ||
| 関谷善文(関谷眼科クリニック・院長) /内川義和(九州保健福祉大学 保健科学部 視機能療法学科) | |||
| VII | 神経眼科 | ||
| 山縣祥隆(兵庫医科大学 眼科・助教授)/調 広子(神戸大学ツ黴眼科) | |||
| VIII | 視能矯正-基礎編 | ||
| 長谷部 聡(岡山大学医学部 眼科・講師) /内海 隆(大阪医科大学 眼科) /瀧畑能子(川崎医療福祉大学 感覚矯正学科・教授川崎医科大学 眼科・講師) /金谷まり子(総合新川橋病院 眼科 視能矯正室) | |||
| IX | 視能矯正-各論 | ||
| 矢ヶ崎悌司(眼科やがさき医院・院長) /野村耕治(兵庫県立こども病院眼科) /黒田紀子(千葉県こども病院 眼科・診療部長) /濱村美恵子(大阪医科大学 眼科) | |||
| X | 眼科検査と視覚補助具 | ||
| 野寄清美(浜松医科大学 眼科) /佐々本研二(京都市立病院 眼科) /仁科幸子(国立成育医療センター 眼科) | |||
| ※以上 10の分野について各章それぞれ過去の問題、解答と解説を収録 | |||
新 糖尿病眼科学一日一課
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho046.htm新 糖尿病眼科学一日一課
 |
初版から7年、糖尿病の治療、眼合併症の診断、治療の進歩に伴い、待望の改訂版刊行!
|
|||||||
執筆者(執筆順)
岩本安彦,岩崎直子,船津英陽(以上,東京女子医科大学)
山下英俊,佐藤武雄,佐藤浩章(以上,山形大学)
山本禎子(東邦大学)
加藤 聡(東京大学)
山本修一(千葉大学)
早川和久(琉球大学)
堀 貞夫(東京女子医科大学)
川崎 良,芳賀真理江(以上,山形大学)
北野滋彦(東京女子医科大学)
福嶋はるみ(東京大学)
須藤史子(埼玉県済生会栗橋病院)
富田剛司(東京大学)
井上賢治(井上眼科病院)
大平明彦(若葉眼科病院)
善本三和子(東京逓信病院)
小松美智子,林 佳枝,鈴木早苗,木所篤子,佐藤あゆみ(以上,東京女子医科大学)
本書の初版が出版されて7年余がたった。この間に糖尿病自体の治療や合併症の診断と治療が大きく変遷し進歩した。 ことに糖尿病網膜症と糖尿病黄斑浮腫の発症と進展に関与するサイトカインの研究が進展し、病態の解明が大きく前進した。これを踏まえて、発症と進展に関与 する薬物療法の可能性を追求する臨床試験が進んでいる。糖尿病網膜症に関しては、以前のように手を着けられないまでに進展した増殖糖尿病網膜症の症例をみ ることが少なくなったように感じる。 一方で、視機能、ことに視力低下に直接つながる糖尿病黄斑浮腫の治療は、現時点で最も論議が活発な病態となっている。硝子体手術やステロイド薬の投与の適 応と効果について、初版が出版された頃に比べると大きく見解が変化している。そして、糖尿病黄斑浮腫の診断に大きな効果を発揮する画像診断装置が普及し た。
改めて、本書が糖尿病眼合併症による失明防止の一助になることを切望する。
(序文より)
内容目次
| I | 糖尿病の病態と疫学 | ||
| 1.糖尿病の代謝異常/2.糖尿病の遺伝相談/3.糖尿病眼合併症の疫学 /4.糖尿病合併症(血管病変)の分子メカニズム | |||
| II | 糖尿病網膜症の病態と診断 | ||
| 1.眼底検査法/2.単純網膜症/3.増殖前網膜症/4.増殖網膜症/5.糖尿病網膜症の硝子体所見/6.糖尿病網膜症の進展速度/7.糖尿病網膜症の進展に関与する因子 | |||
| III | 網膜症の補助診断法 | ||
| 1.FAG施行上の注意点/2.ICG螢光眼底造影/3.糖尿病網膜の電気生理検査/4.糖尿病における網膜循環/5.糖尿病網膜症における超音波画像診断/6.糖尿病眼におけるバリア機能測定/7.OCT検査法/8.その他の画像解析(RTA,SLO) | |||
| IV | 糖尿病網膜症の病期分類 | ||
| 1.Scott分類/2.福田分類/3.Davis分類/4.ETDRS分類 | |||
| V | 糖尿病網膜症の治療 | ||
| 1.網膜症の治療方針/2.糖尿病網膜症と血糖コントロール/3.糖尿病網膜症の薬物治療の可能性/4.選択的光凝固法/5.汎網膜光凝固(PRP)/6.硝子体手術の概念-対象,ゴール/7.糖尿病網膜症に対する硝子体手術/8.硝子体手術機器の解説 | |||
| VI | 糖尿病黄斑症 | ||
| 1.黄斑症の疫学/2.病理と病態/3.薬物療法/4.光凝固療法/5.硝子体手術/6.その他の治療法/7.黄斑沈着 | |||
| VII | 糖尿病と白内障 | ||
| 1.糖尿病白内障/2.白内障手術適応と血糖コントロール/3.白内障手術と糖尿病網膜症 | |||
| VIII | その他の糖尿病眼合併症 | ||
| 1.血管新生緑内障の病態/2.血管新生緑内障の治療/3.糖尿病性角膜症/4.糖尿病虹彩症と糖尿病虹彩炎/5.糖尿病による視神経障害/6.眼球運動障害/7.屈折・調節異常 | |||
| IX | 網膜症と関連疾患 | ||
| 1.網膜静脈閉塞症と糖尿病/2.腎症と網膜症/3.神経障害/4.糖尿病合併妊婦の網膜症管理/5.高血圧/6.1型糖尿病 | |||
| X | 糖尿病網膜症による中途失明 | ||
| 1.中途視覚障害の原因としての糖尿病網膜症/2.網膜症患者の心理・社会的問題とソーシャルワーク支援/3.中途視覚障害者のリハビリテーション/4.糖尿病網膜症に対するロービジョン外来/5.社会資源・社会復帰施設一覧 | |||
| XI | 糖尿病眼科における看護 | ||
| 1.外来における看護/2.病棟における看護/3.手術室における看護 | |||