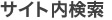‘書籍案内’ 一覧
コンタクトレンズフィッティングテクニック
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho047.htmコンタクトレンズフィッティングテクニック
 |
この本があれば、明日からのコンタクトレンズ診療は安心して出来る!
品切れ |
|||||||
内容目次
| 1 | コンタクトレンズの処方に必要な角膜の知識 | ||
| 2 | コンタクトレンズの処方に必要な涙液の知識 | ||
| 3 | コンタクトレンズの処方に必要な屈折・矯正の知識 | ||
| 4 | コンタクトレンズの処方に必要なその他の知識 | ||
| 5 | コンタクトレンズの選択 | ||
| 6 | ハードコンタクトレンズ(HCL)の処方 [症例 1] | ||
| 7 | フルオレセインパターンの判定方法 | ||
| 8 | ハードコンタクトレンズ(HCL)の処方[症例 2] | ||
| 9 | レンズデザインと角膜形状 | ||
| 10 | ハードコンタクトレンズ(HCL)の処方[症例 2(続)] | ||
| 11 | フルオレセインパターンの判定法における注意点 | ||
| 12 | ベベル・エッジのチェック<Ⅰ> | ||
| 13 | ベベル・エッジのチェック<Ⅱ> | ||
| 14 | ベベル・エッジのチェック<Ⅲ> | ||
| 15 | ベベル・エッジのチェック<Ⅳ> | ||
| 16 | ベベル・エッジのチェック<Ⅴ> | ||
| 17 | ソフトコンタクトレンズ(SCL)の処方 | ||
| 18 | ソフトコンタクトレンズ(SCL)の種類 | ||
| 19 | ソフトコンタクトレンズ(SCL)の選択 | ||
| 20 | コンタクトレンズと定期検査 | ||
| 21 | コンタクトレンズ(CL)と眼障害 | ||
| 22 | ハードコンタクトレンズの修正とは? | ||
| 23 | 修正によるHCLの苦情処理-くもり(1) | ||
| 24 | 修正によるHCLの苦情処理-くもり(2) | ||
| 25 | 修正によるHCLの苦情処理-充血 | ||
| 26 | 修正によるHCLの苦情処理-異物感(1) | ||
| 27 | 修正によるHCLの苦情処理-異物感(2) | ||
| 28 | 修正によるHCLの苦情処理-視力 | ||
| 29 | SCLの苦情処理-くもり・かすみ・視力低下 | ||
| 30 | SCLの苦情処理-異物感・眼痛・流涙・充血 | ||
| 31 | 乱視に対するコンタクトレンズの処方 | ||
| 32 | ドライアイ | ||
| 33 | ラウンドコルネア | ||
| 34 | カラーコンタクトレンズ | ||
| 35 | 治療用ソフトコンタクトレンズの処方 | ||
| 36 | 無水晶体眼に対するコンタクトレンズの処方 | ||
| 37 | 乳幼児・小児に対するコンタクトレンズ の処方 | ||
| 38 | 光彩付きコンタクトレンズ・義眼コンタク トレンズの処方 | ||
| 39 | ハードタイプ・バイフォーカルコンタクトレンズの処方 | ||
| 40 | ソフトタイプ・バイフォーカルコンタクトレ ンズの処方 | ||
| 41 | HCLのカスタムメイドの処方 | ||
| 42 | コンタクトレンズと点眼薬 | ||
| 43 | コンタクトレンズとケア用品 | ||
| ●ワンポイント(15項目) | |||
斜視 Q&A101
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho048.htm斜視 Q&A101
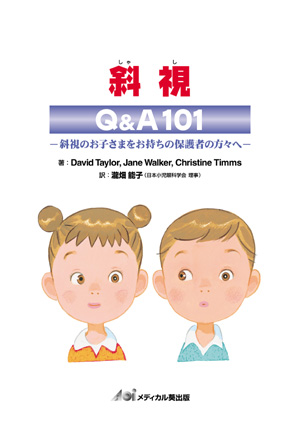 |
斜視のお子さまをお持ちの保護者の方々へ!
|
|||||||||
この本は、斜視のお子さまをお持ちの保護者の方々から寄せられた多くの質問をまとめたものです。不思議なことに斜視のお子さまの保護者は、もっと重症な眼 疾患を持っておられる方々よりも深刻に悩んでおられるように思えることがあります。わたしたちはその悩みをひとつひとつ解決し、斜視についての理解の手助 けができれば、と考えています。 この本では、保護者の方々からの斜視についての質問にわかりやすく答えるようにしました。中には、答えるのが、大変難し い質問もありました。それは、斜視について間違った知識が信じ込まれているからであると感じ、このような斜視に対する間違った情報をなくしていかなければ ならないと痛感しました。
(著者序文より)
ロンドンの小児病院でTaylor先生に小児眼科を教えていただいていた時に、私はとても感動したことがありました。Taylor先生の外来では、保護者 の方々がお子さまの眼疾患について熱心に勉強し、正しく理解し、小児眼科医やナース、視能訓練士と一緒に治療していくのです。
この本は、保護者の方々のための斜視のガイドブックをTaylor先生らが書かれたものです。保護者の方々はしっかり勉強し、疑問点は納得できるまで質問していました。
101のQ&Aの中には日本ではありえないようなものもありましたので、少し日本風にアレンジし、イラストも加えました。この本が斜視のお子さまをお持ちの方々にとって少しでも役立てば、と願っております。
(訳者序文より)
内容目次
| A | 斜視についての一般的な質問(Q&A 1~22) | ||
| B | 斜視の影響(Q&A 23~30) | ||
| C | 診断と分類(Q&A 31~35) | ||
| D | 手術以外の治療(Q&A 36~71) | ||
| E | 斜視手術(Q&A 72~101) | ||
| F | 眼振(眼球振盪)についての質問 | ||
視能訓練士-スペシャリストへの道<3>
2010年4月19日 月曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho049.htm視能訓練士-スペシャリストへの道<3>
国家試験問題集・解答と解説 平成15~17年版
- その他の『視能訓練士-スペシャリストへの道』はこちら
 |
わかりやすい2色刷 詳細な解説 平成15~17年の過去問題を分野別に収録 受験生必携の書!
|
|||||||
執筆者(五十音順)
鵜飼一彦(早稲田大学理工学部 教授)
内川義和(九州保健福祉大学保健科学部 視機能療法学科 講師)
内海 隆(大阪医科大学 眼科 講師)
金谷まり子(元 総合新川橋病院 眼科 視能矯正室 主任)
川瀬芳克(愛知淑徳大学医療福祉学部 教授)
黒田紀子(千葉県こども病院 診療部長)
調 広子(神戸大学附属病院 眼科)
菅澤 淳(大阪医科大学 眼科 助教授)
関谷善文(関谷眼科クリニック 院長)
瀧畑能子(川崎医療福祉大学 感覚矯正学科 教授・川崎医科大学 眼科 講師)
仁科幸子(国立成育医療センター 眼科)
野村耕治(兵庫県立こども病院 眼科 医長)
濱村美恵子(大阪医科大学附属病院 眼科)
林 孝雄(帝京大学医療技術学部 視能矯正学科 教授)
平井淑江(愛知淑徳大学医療福祉学部 教授)
福山千代美(日本大学附属板橋病院 視能訓練室 主任)
母坪雅子(札幌きい眼科 院長)
溝部恵子(京都第二赤十字病院 眼科 部長)
矢ヶ崎悌司(眼科やがさき医院 院長)
山縣祥隆(兵庫医科大学 眼科 助教授)
山下牧子(東京医科歯科大学医学部 眼科)
横山 連(大阪市立総合医療センター 小児眼科 部長)
若山曉美(近畿大学医学部附属病院 眼科)
視能訓練士の有資格者は年々増えて5,000人を突破しました。ただ国家試験に合格して視能訓練士の資格を得ても、すぐに日常外来で一人前の視能訓練士として役立つわけではなく、スペシャリストの道は奥深いので、多くの臨床の場にあたって勉強や経験をつむ必要があります。
今回の第3版においても、日本弱視斜視学会、日本視能矯正学会などで活躍されている先生方、視能訓練士の方々にご協力をお願いしまして、各問題の解答とと もに理解しやすいように解説を加えていただきました。したがって、本書は単なる試験問題の解答集ではなくて、索引を活用して日常診療における参考書として も利用できるものと思っております。なお、試験問題の解答については、それぞれの担当者が出題者の立場を考えながら、問題点のある場合は編集協力者と相談 の上、解説を加えて解答したもので、厚生労働省から発表された正解と多少異なっている例もあるかと思います。この点については、解説を読んでいただき担当 者の意を汲み取って下されば幸いです。
本書が視能訓練士ならびに視能訓練士国家試験受験関係者に広く利用され、役立つことを願っています。
内容目次
| <平成15・16年> | |||
| I | 発達臨床心理学 | ||
| II | 視器の解剖と生理 | ||
| III | 眼の機能 | ||
| IV | 生理光学 | ||
| V | 眼科疾患 | ||
| VI | 眼薬理 | ||
| VII | 神経眼科 | ||
| VIII | 視能矯正-基礎編 | ||
| IX | 視能矯正-各論 | ||
| <平成17年> | |||
| I | 基礎医学大要(旧のⅠ,Ⅱ,Ⅵ) | ||
| II | 基礎視能矯正学(旧のⅢ,Ⅳ) | ||
| III | 視能検査学(旧のⅧ,Ⅹ) | ||
| IV | 視能障害学(旧のⅤ,Ⅶ) | ||
| V | 視能訓練学(旧のⅨ) | ||
| ※旧問題系、新問題系の各分野の全ての問題,解答と解説を収録 | |||
眼内レンズを科学する
2010年4月16日 金曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho050.htm眼内レンズを科学する
 |
|
|||||||
白内障手術は紀元前から行われていたという.脳から濁った液が流れてたまったのが白内障だと考えられ,硝子体中に落下させる「倒下法」が行われた.近代に なって水晶体嚢内摘出術と嚢外摘出術の術式選択に論争が繰り返し行われた.現代に比べて手術機器のみならず術式も確立されていなかったが,何よりも手術結 果で不足したのが術後の視機能の不完全なことである.眼鏡やコンタクトレンズによる術後視力の矯正手段に問題があった.
やがて眼内レンズ挿入術が登場することとなる.術後のquality of visionの改善は目覚しいものであった.眼内レンズが高く評価され,現在のような小切開foldable眼内レンズ,着色レンズ,非球面レンズ,そし て調節性レンズの開発など今後も発展し続けるに違いない.しかし,新しい眼内レンズの開発や臨床成績に注意を傾けるあまり,眼内レンズについての基本的知 識を系統的に知る機会が少ないように思われる.眼内レンズのバイブルとなる専門書が刊行されていないことから,本書では基礎から臨床にわたって眼内レンズ を基本からしっかりと知るための手伝いが欲しいと思った次第である.
本書では,眼内レンズの歴史,視機能上の役割・利点,デザイン材質と特性,生体適合性,眼内レンズの作製法,減菌法,各種眼内レンズの特徴,眼内レンズ挿 入法,後発白内障,屈折矯正手術用眼内レンズ,多重手術と眼内レンズの観点から眼内レンズを12項目にわたって徹底的に科学的に分析した.各項目の担当者 として,各分野で造詣の深い第一線で活躍中の方々に執筆をお願いした.その結果,わかりやすい内容にまとめられているので,日常診療に役立つと確信してい る.本書が眼内レンズの百科辞典的存在として活用されることを期待している.
(序文より)
内容目次
| I | 眼内レンズの歴史 | ||
| II | 眼内レンズの視機能上の役割・利点 | ||
| III | 眼内レンズのデザイン、材質と特性 | ||
| 1.デザイン/2.材質/3.光学的特性/4.物理的特性 | |||
| IV | 眼内レンズと生体適合性 | ||
| 1.眼内レンズに対する生体反応と生体適合性/2.術後炎症反応/3.眼内レンズと水晶体上皮細胞の反応 | |||
| V | 眼内レンズ作製法 | ||
| VI | 眼内レンズ滅菌法 | ||
| VII | 眼内レンズと視機能 | ||
| 1.収差/2.コントラスト感度/3.グレア・ハロー/4.屈折度誤差/5.偽調節/6.色感覚/7.偏位/8.グリスニング/9.混濁(着色現象)10.網膜障害(光酸化) | |||
| VIII | 各種眼内レンズの特徴 | ||
| 1.Foldable眼内レンズのいろいろ/2.多焦点眼内レンズ/3.Toric眼内レンズ/4.調節性眼内レンズ/5. 非球面眼内レンズ/6.極小切開用眼内レンズ/7.無虹彩用眼内レンズ/8.縫着用眼内レンズ/9.水晶体嚢拡張リング | |||
| IX | 眼内レンズと挿入法 | ||
| X | 眼内レンズと後発白内障 | ||
| 1.後発白内障の解析法(PCO)/2.最近の眼内レンズと後発白内障/3.後発白内障の物理的・化学的抑制方法 | |||
| XI | 屈折手術用眼内レンズ | ||
| 1.前房レンズ/2.後房レンズ | |||
| XII | 多重手術と眼内レンズ | ||
| 1.角膜移植同時手術とIOLの選択/2.緑内障手術と眼内レンズ/3.網膜硝子体手術と眼内レンズ/4.ぶどう膜炎と眼内レンズ | |||
| 白内障手術は紀元前から行われていたという.脳から濁った液が流れてたまったのが白内障だと考えられ,硝子体中 に落下させる「倒下法」が行われた.近代になって水晶体嚢内摘出術と嚢外摘出術の術式選択に論争が繰り返し行われた.現代に比べて手術機器のみならず術式 も確立されていなかったが,何よりも手術結果で不足したのが術後の視機能の不完全なことである.眼鏡やコンタクトレンズによる術後視力の矯正手段に問題が あった. やがて眼内レンズ挿入術が登場することとなる.術後のquality of visionの改善は目覚しいものであった.眼内レンズが高く評価され,現在のような小切開foldable眼内レンズ,着色レンズ,非球面レンズ,そし て調節性レンズの開発など今後も発展し続けるに違いない.しかし,新しい眼内レンズの開発や臨床成績に注意を傾けるあまり,眼内レンズについての基本的知 識を系統的に知る機会が少ないように思われる.眼内レンズのバイブルとなる専門書が刊行されていないことから,本書では基礎から臨床にわたって眼内レンズ を基本からしっかりと知るための手伝いが欲しいと思った次第である. 本書では,眼内レンズの歴史,視機能上の役割・利点,デザイン材質と特性,生体適合性,眼内レンズの作製法,減菌法,各種眼内レンズの特徴,眼内レンズ挿 入法,後発白内障,屈折矯正手術用眼内レンズ,多重手術と眼内レンズの観点から眼内レンズを12項目にわたって徹底的に科学的に分析した.各項目の担当者 として,各分野で造詣の深い第一線で活躍中の方々に執筆をお願いした.その結果,わかりやすい内容にまとめられているので,日常診療に役立つと確信してい る.本書が眼内レンズの百科辞典的存在として活用されることを期待している. (序文より) |
ヌンチャク型シリコーンチューブ -私のポイント- 涙道手術と眼瞼下垂症手術
2010年4月16日 金曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho051.htmヌンチャク型シリコーンチューブ-私のポイント-涙道手術と眼瞼下垂症手術
 |
|
|||||||
執筆者(掲載順)
栗橋克昭,成岡純二,大野木淳二,永原幸,宮久保純子,宮崎千歌,中川喬,廣瀬美央,五嶋摩理,今野公士,忍足和浩,河合憲司,黒田真一郎,寺西千尋,上 岡康雄,田中謙剛,森寺威之,保手浜靖之,新田安紀芳,湯田兼次,芳賀照行,舘奈保子,原吉幸,西條正城,岡和田紀昭,平山健太郎,波多野吟哉,植木麻理
つい最近まで,流涙症の治療は一握りの眼科医により細々と行われ,眼科診療のはみだし者だった。しかも,涙道狭窄を憎悪させる金属ブジーが普及し,ブジー で治らない場合に涙嚢鼻腔吻合術が唯一の治療法として認められていた.チューブ挿入術は有用であるが認知されなかったのは,正しく涙道に挿入することがむ ずかしく,かつ挿入が困難であったためである.
この状態を一新させたのが栗橋克昭先生のヌンチャク型シリコーンチューブ(NST)である.このNSTの導入により流涙症の治療が容易となり,普及したの は,わが国ばかりでなく世界的な業績である.私自身も手製または市販のCrawford型チューブを長年苦労して使用していた.その頃を思うと隔世の感が ある.流涙症のファーストチョイスはNSTとしているので,すでに5,000例余りに使用している.これにより涙嚢鼻腔吻合術は流涙症症例の10%以下に 減少した.涙小管閉塞が治らない場合はJones Tubeを使用しているが,その比率も低下している.
NSTが発表されてから14年余りがたち,NSTについての「総括の時期」に入っている.このたび本書が刊行されるのは流涙症に悩む患者さん,眼科医にとって朗報である.NSTを理解するには欠かすことのできない本であり,ぜひ座右の書として欲しい.
NSTは侵襲が少なく,高齢者にも外来で容易にできる治療法である.流涙症の初期には特に有効であり,侵襲が大きなDCRやJones Tubeの対象となる症例を減らすことができる.早期診断とNSTによる早期治療が肝要である.
(推薦のことば:札幌医科大学 名誉教授 中川 喬)
内容目次
| I | 総論 涙嚢鼻腔吻合術【栗橋克昭】 | ||
| 1.涙道手術(含:眼瞼下垂症手術)2.NST-新しい涙道手術のために(含:眼瞼下垂症手術) | |||
| II | 総論 | ||
| 1.NST挿入術のための臨床解剖の重要性/2.涙道道の臨床解剖-NST挿入時の注意点/3.DSIの適応とNST挿入手技 | |||
| III | 「解剖」を中心として | ||
| 1.NST挿入術に役立つ涙道内視鏡検査/2.涙道内視鏡と鼻内視鏡を使用した涙道診療/3.NSTと涙小管閉塞の治療/4.小児の涙道疾患の診断と治療 | |||
| IV | 「手術手技」を中心として | ||
| 1.NSTをはじめて使用する人のために/2.術式によるNST使用法/3.NSTの手術手技の実際/4.NST手術手技の問題点/5.NSTの適応と手技的な注意点/7.チュービングの奏効機序と挿入テクニック/8.鼻内視鏡下に確実に行うNST留置法と鼻腔内からの抜去法/9.DSIの実際/10.NSTの特長を生かした挿入法/11.NST単独で成功率を上げるために/12.NST挿入法/13.鼻内視鏡の活用法/14.涙道内視鏡を活用NST挿入術/15.NSTと眼球突出/16.涙嚢鼻腔吻合術鼻内法および小児の涙道治療/17.先端湾曲涙洗針ブジーと先端湾曲NST挿入術 | |||
| V | 「症例」を中心として | ||
| 1.NST施行95例の臨床的検討/2.NSTの使用経験-先天性鼻涙管閉塞症の治療/3.涙道内視鏡下NST挿入術を施行した鼻涙管閉塞症例 | |||
| 追補:涙道閉塞疾患と眼瞼下垂症 | |||
視能訓練士-スペシャリストへの道<4>
2010年4月16日 金曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho052.htm視能訓練士-スペシャリストへの道<4>
国家試験問題集・解答と解説 平成18年版
- その他の『視能訓練士-スペシャリストへの道』はこちら
 |
今年度もわかりやすい2色刷
|
|||||||||
執筆者(五十音順)
有若由加理(島本眼科医院)
礒辺真理子(千葉県こども病院眼科)
稲垣尚恵(大阪医療センター附属視能訓練学院)
鵜飼一彦(早稲田大学理工学部)
内 川義和(九州保健福祉大学保健科学部)
内海隆(内海眼科医院)
金谷まり子(元 総合新川橋病院眼科)
川瀬芳克(愛知淑徳大学医療福祉学部)
木村亜紀子(兵庫医科大学)
菅澤淳(大阪医科大学)
杉山能子(金沢大学医学部)
関谷 善文(関谷眼科クリニック)
田邊宗子(愛知淑徳大学医療福祉学部)
中前美佳(大阪大学医学部附属病院眼科)
仁科幸子(国立成育医療センター眼科)
野村耕治(兵庫県立こども病院)
濵村美恵子(大阪医科大学附属病院眼科)
林孝雄(帝京大学医療技術学部)
平井淑江(愛知淑徳大学医療福祉学部)
母 坪雅子(札幌きい眼科)
溝部恵子(京都第二赤十字病院眼科)
横山連(大阪市立総合医療センター小児眼科)
視能訓練士国家試験が施行されてから30余年になりますが,平成17年からは試験問題の分野が,以前の発達臨床心理学,視器の解剖と生理,目の機能など9 分野から,基礎医学大要,基礎視能矯正学などの5分野に変更されました.また,今年度からは,記述式の問題がなくなって,選択肢式の問題となり問題数も増 えました.そこで昨年までの問題解答と解説集は3年分をまとめて一冊にしておりましたが,今年からは1年分で一冊にまとめました.
今回も本書に関して日本弱視斜視学会,日本視能矯正学会などで活躍されている先生方,視能訓練士の方々に執筆のご協力をお願いして,各問題の解答ととも に問題に関連する事柄の解説を理解しやすくまとめていただきました.なお,試験問題の解答については,それぞれの担当者が出題の意図を考えながら,問題点 のある場合は編集協力者とも相談して,
解説を加えて解答したもので,厚生労働省から発表された正解と多少異なっている場合があるかもわかりません.この点については解説を読んでいただき,解答者の意を汲み取って下されば幸いです.
本書は単なる試験問題解答集ではなくて,索引を活用して日常診療における参考書としても利用できるものと思っております.このことから本書が視能訓練士ならびに視能訓練士国家試験受験関係者に広く利用され,役立つことを願っております.
(序文より)
内容目次
| I | 基礎医学大要 | ||
| II | 基礎視能矯正学 | ||
| III | 視能検査学 | ||
| IV | 視能障害学 | ||
| V | 視能訓練学 | ||
眼科医療事故の法的責任
2010年4月16日 金曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho053.htm眼科医療事故の法的責任
 |
眼科における医療事故紛争への対処を明解に示した眼科医必携の書!
|
|||||||
診療に携わる者にとって,最も不愉快なのはトラブルに巻き込まれることである.医師は常に患者にとって善かれと思って診療 しているのであるが,予想し得ない結果を招けば紛争となり,時には訴訟にまで発展してしまう.
医師に不注意がある一方で,不条理なことを要求する訳の分からぬ患者もいる.したがって,医師の方でもある程度の法的知 識を持って診療に当たらねばならない.眼科専門医認定試験でも社会・予防医学として例年出題されている.近年,医師ばかりでなく医療従事者の量産時代に 入っているから,相対的レベル低下をきたし,診療トラブルの増加に拍車がかかっている.そのような理由から,医療のリーダーである医師には監督責任も問わ れる機会が多くなりつつある.
深谷 翼氏は長らく医事紛争を専門としてこられた方で,臨床各科における雑誌に医事法関係の論文を多数発表され,これまで『医療関係者のための医療事故と法的責 任』,『最新事例に学ぶ医療訴訟対策』,『医療事故の法的基礎知識と医療訴訟最新判例解説集』といった成書を上梓されている.これらの書籍にも眼科関連の 症例の記載があるが,かつて私が編集した『眼科保健医療ガイド』でも「医事紛争とその防止」を分担執筆していただいた.
日常診療においてどのように患者に接したら良いか,医事紛争に関わらないためにどうするか,訴訟になってもどうしたら不利にならないかを知るには適切な本であり,眼科医に推薦したい一冊である.
<推薦のことば> 丸尾敏夫(帝京大学医療技術学部長)
内容目次
| 第1部 基礎知識編 | |||
| I | 眼科医療事故訴訟の現況 | ||
| II | 眼科医療事故と法的責任 | ||
| III | 眼科医療事故と民事責任(損害賠償責任) | ||
| 1. 一般的不法行為/2. 特殊的不法行為/3. 債務不履行/4. 損害賠償責任/5. 眼科医療事故と解決方法 | |||
| IV | 眼科医療事故と刑事責任 | ||
| 1. 眼科医療事故と犯罪/2. 眼科医療事故と刑罰 | |||
| 第2部 事例編 | |||
| I | 問診・検査 | ||
| 1. 抗生物質注射による薬疹事故と医師の問診義務/2. 未熟児網膜症による視力障害と診療の適否 | |||
| II | 診断 | ||
| 1. 緑内障による失明と医師の責任の有無/2.多発性後極部網膜色素上皮症と/診療過誤の有無/3. 未熟児網膜症を白内障と誤診した医師の責任/4. 流行性角結膜炎患者の/角膜穿孔による失明と医師の責任/5. 角膜ヘルペスと診療過誤の有無 | |||
| III | 説明義務(インフォームド・コンセント) | ||
| 1. 球結膜腫瘤手術と合併症に対する説明義務 /2. 糖尿病網膜症患者に対する硝子体手術と医師の説明義務/3. 検査結果と眼科医の告知説明義務の有無/4. RK手術(放射状角膜切開術)の/施行と事前告知(説明)義務 | |||
| IV | 治療 | ||
| 1.眼瞼下垂症に対する治療の適否/2.細菌性(緑膿菌性)角膜潰瘍と医師の治療上の過失/3. 右眼打撲症に対する処置の適否/4.未熟児網膜症による視力障害と治療責任/5. 内因性細菌性眼内炎に対する診療の適否/6. コンタクトレンズ装用による左眼損傷と医師の責任 | |||
| V | 薬剤 | ||
| 1. 糖尿病患者の角膜ヘルペスとステロイド薬の投与/2. ステロイド剤点眼薬投与とステロイド緑内障等の罹患の有無 | |||
| VI | 手術 | ||
| 1. 白内障等の手術後失明と医師の責任/2. 蓄膿症手術後の失明と眼科医の責任/3. 近視矯正のためのレーシック手術の適否/4. 角膜移植手術後の緑内障発症と医師の過失/5. 網膜剥離に対する緊急手術の要否 | |||
| VII | 術後(術前)管理 | ||
| 1. 緑膿菌感染による左眼失明と診療過誤の有無/2. 術後眼内炎の発症と医師の過失 | |||
| VIII | 転医(送)・その他 | ||
| 1. 未熟児網膜症による失明と眼科医の責任/2.見習看護師の調剤ミスと眼科医の刑事責任 | |||
| <資料> 日本弁護士連合会報酬等基準 | |||
眼瞼学 眼瞼下垂症手術
2010年4月16日 金曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho054.htm眼瞼学 眼瞼下垂症手術
 |
眼瞼下垂手術の目的は形態の矯正よりも,全身機能の改善にあるという革新的なエビデンスの集積!
|
|||||||
眼瞼下垂症は形態的な疾患であるという従来からの概念を打破し,眼科医にインパクトを与える本書が刊行されるの は喜ばしいかぎりである。患者さんの生の声で,手術の画像を見聞きできる斬新なスタイルは今後の手術書の先駆と思 われる。
栗橋克昭先生が最近4,5年学会で眼瞼下垂症のセッションを開催し,発表された集大成が本書である。
信州大学形成外科教授の松尾 清先生が開瞼のメカニズムについて,革新的な研究を発表されている。松尾教授によ ると,眼瞼下垂の手術の目的は形態の矯正よりは全身機能の改善にあり,手術により主に自律神経障害の改善が 期待できると述べられている。栗橋先生は眼瞼下垂が顕性となる前の代償期の症例の手術効果につき検討し,松尾理 論を支持する結果を得ている。
先生は涙液分泌テストである綿糸法の開発や流涙症の診断,治療の新しい手法を考案され,これらの分野での先駆 者でもある。
本書は個々の症例のエビデンス集でもある。私どもも,うつ病が眼瞼下垂症手術後に軽快し,治療薬が不用になった 症例や,自律神経症状が軽快した症例を経験している。個々の患者さんの病態を把握し,生の声を分析することが臨床 のエビデンスになり,臨床医学の出発点となる。
<推薦のことば> 札幌医科大学 名誉教授 中川 喬
内容目次
| 序説:眼瞼下垂症手術の新しい展開 | |||
| 第一部:眼瞼下垂症手術と自律神経機能検査 | |||
| I | はじめに | ||
| II | 睫毛クリップ負荷テスト | ||
|
1 .睫毛クリップ負荷テストについて/2 .睫毛クリップ負荷テストに用いるクリップ
|
|||
| III | 涙液分泌テスト | ||
| 1.綿糸法/2.TMH(含:フルオレセイン色素残留テスト)/3.濾紙法(含:フルオレセイン色素残留テスト) | |||
| IV | 眼瞼下垂症手術 | ||
|
1.はじめに
3.究極の眼瞼下垂症手術をめざして
|
|||
| 第二部:症例編-全身機能改善への道 | |||
| 症例1-肩こり,不眠,鬱が改善/ | |||
| 症例2-肩こり,頭痛,左上肢のしびれが楽になった/ | |||
| 症例3-狭心症が良くなり,髪が黒くなり,短期記憶が良くなった/ | |||
| 症例4-流涙症が治り,涙道再建手術の完成をみた/ | |||
| 症例5-多彩な症状を有する腱膜性眼瞼下垂症(代償期)が改善された/ | |||
| 症例6-糖尿病性壊疽で左足を切断,右足にも壊疽が起こる,右足は温かくなり,杖なしで歩けるようになった/ | |||
| 症例7-両眼視力が改善,下腿静脈瘤が良くなった/ | |||
| 症例8-アトピー性皮膚炎が改善された,正座が長時間できるようになり,耳鳴りも改善した/ | |||
| 症例9-95歳の男性,楽に歩けるようになった/ | |||
| 症例10-強い下腿浮腫と肩こりが改善された/ | |||
| 症例11-下腿浮腫が改善され,スイスイと歩けるようになった/ | |||
| 症例12-手が温かく,赤くなり,冷え症,便秘,ドライアイが改善された/ | |||
| 症例13-小学4年のとき,事故で半身不随になるかもしれないといわれた.成人になってから,いろいろな症状が出てきた.術後,肩こり,頭痛,腰痛などがとれた/ | |||
| 症例14-線維筋痛症に特徴的な18カ所の圧痛点すべてに圧痛を認めた(全身の痛み,強い肩こり,短期記憶力低下,爪の凹凸など)が,術後,すべてが改善した.両裸眼視力も良くなった/ | |||
| 症例15-頭痛,不眠,憂鬱などさまざまな症状が続き,8日間,食物も水も受けつけず,生命の危機を感じていた.術後,熟睡でき,食欲も出てきた/ | |||
| 症例16-約1年前に発症した右突発性難聴が術直後から良くなった/ | |||
| 症例17-緑内障による視野狭窄が改善した。白髪が黒くなった。老人のような歩き方が治った/ | |||
| 症例18-鬱病が改善した.同時に肩こり,頭痛,冷え症が良くなった/ | |||
| 症例19-炭酸ガスレーザーを使用し,9mm切開で行った低侵襲眼瞼下垂症手術.眼瞼下垂症手術は眼輪筋の剥離で決まる。 | |||
視能訓練士-スペシャリストへの道<5>
2010年4月16日 金曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho055.htm視能訓練士-スペシャリストへの道<5>
国家試験問題集・解答と解説 平成19年版
- その他の『視能訓練士-スペシャリストへの道』はこちら
 |
受験生必携!判りやすいと好評のメディカル葵出版の視能訓練士試験問題集!!
|
|||||||||
執筆者(五十音順)
礒辺真理子(千葉県こども病院眼科)
稲垣尚恵(大阪医療センター附属視能訓練学院)
鵜飼一彦(早稲田大学先進理工学部)
内川義和(九州保健福祉大学保健科学部)
内海隆(内海眼科医院)
金谷まり子(東邦大学医療センター佐倉病院眼科)
木村亜紀子(兵庫医科大学)
菅澤淳(大阪医科大学)
杉山能子(金沢大学医学部)
関谷善文(関谷眼科クリニック)
田邊宗子(愛知淑徳大学医療福祉学部)
中前美佳(藍野病院視能訓練士)
仁科幸子(国立成育医療センター眼科)
野村耕治(兵庫県立こども病院眼科)
濵村美恵子(大阪医科大学附属病院眼科)
林孝雄(帝京大学医療技術学部)
平井淑江(愛知淑徳大学医療福祉学部)
福山千代美(日本大学板橋病院視能訓練室)
母坪雅子(札幌きい眼科)
溝部恵子(京都第二赤十字病院眼科)
山縣祥隆(山縣眼科医院)
横山連(大阪市立総合医療センター小児眼科)
国家試験問題の作成にあたっては,多くの選ばれた試験委員の方がそれぞれ何題かの問題を作って,その中から適切と考えられる 試験問題が厳選されて出題されることになります.試験委員の先生は問題が適切か,間違いないか,よく検討されて決定されますが, ときには解答ができないような問題であったり,厚生労働省の正解が間違っているのでないかという問題が混じってくることがあり ます.
今回の国家試験問題では厚生労働省が不適切問題として数題あげていますが,そのほかにも,本書の執筆者である数人の先生から 不適切問題ではないかとご指摘をいただいた問題があります.「問題解説」のところで,執筆された先生の意見が記載されています. 国家試験で,このように不適切と思われる問題が多く出ることは,今までに経験がなく,受験者も解答するのに悩まれたのではない でしょうか.試験委員の先生方も試験問題の作成ならびに選定にたいへん苦労されていると思いますが,よろしくお願いしたいと 考えます.
本書には毎年,索引をつけていますので,単に試験勉強のみならず,解説部分が日常診療の参考書としても利用していただけるもの と思っています.本書が弱視斜視や視能訓練の関係者に広く利用され,役立つことを願っております.
(序文より)
内容目次
| I | 基礎医学大要 | ||
| II | 基礎視能矯正学 | ||
| III | 視能検査学 | ||
| IV | 視能障害学 | ||
| V | 視能訓練学 | ||
| ※すべての問題に解答と解説を付与,カラー写真問題もそのまま掲載(分野ごとに整理されているため,実際の出題順とは違っています) | |||
涙嚢鼻腔吻合術と眼瞼下垂症手術 Ⅰ 涙嚢鼻腔吻合術
2010年4月16日 金曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho056.htm涙嚢鼻腔吻合術と眼瞼下垂症手術 Ⅰ 涙嚢鼻腔吻合術
 |
涙器疾患の研究,診療の最新情報!
|
|||||||
内容目次
| I | 総論 涙嚢鼻腔吻合術【栗橋克昭】 | ||
| 1.はじめに/2.涙嚢鼻腔吻合術鼻外法(DCR鼻外法)/3.全涙道再建術/4.DCR鼻内法(下鼻道法)/5.DCR涙小管法(中鼻道法)/6.レーザー涙嚢篩骨洞吻合術涙小管法/7.おわりに | |||
| II | NST挿入術の戦略【湯田兼次】 | ||
| 1.三種の神器/2.基本手技/3.戦略 | |||
| III | 内視鏡的DCR鼻外法【保手浜靖之】 | ||
| 1.DCRの適応/2.内視鏡的DCR鼻外法に使用する器具/3.内視鏡的DCR鼻外法の準備/4.内視鏡的DCR鼻外法の手術法/5.術後薬/6.術後処置 | |||
| IV | 涙嚢鼻腔吻合術鼻外法の位置づけと必要な手技【上岡康雄】 | ||
| 1.涙道閉塞治療におけるDCR鼻外法の位置づけ/2.術前検査および処置/3.手術器具/4.手術手技/5.手術を成功させるためのポイント | |||
| V | 涙嚢鼻腔吻合術(DCR)鼻外法-十分な大きさの吻合孔(リノストミー)を維持するための工夫-【大野木淳二】 | ||
| 1.手術手技/2.術後合併症/3.術後管理/4.術後評価法 | |||
| VI | 涙嚢鼻腔吻合術(鼻内法)【張 國中】 | ||
| 1.手術適応/2.術前検査/3.手術器具/4.術前のセッティング/5.涙嚢の鼻腔内での位置/6.麻酔/7.手術手技/8.合併症/9.手術成績/10.再閉塞症例に対する再手術 | |||
| VII | 涙嚢鼻腔吻合術鼻内法(中鼻道法)【原 吉幸】 | ||
| 1.鼻内法手術適応/2.前眼部処置/3.涙嚢の同定/4.鼻腔内の麻酔/5.粘膜切開/6.骨窓作製/7.涙嚢切開/8.ステント挿入/9.手術終了時/10.術後のケア | |||
| VIII | 涙嚢鼻腔吻合術鼻内法(下鼻道法)【永原 幸】 | ||
| 1.涙道の構造および機能の概要/2.臨床経過の把握/3.涙道検査と治療戦略 | |||
| IX | 涙嚢鼻腔吻合術下鼻道法の術式【宮久保純子】 | ||
| 1.用意する器具/2.麻酔/3.手術手順/4.術後管理 | |||
| X | 涙嚢鼻腔吻合術(DCR)下鼻道法-安全かつ確実な治療法の工夫-【大野木淳二】 | ||
| 1.術前検査/2.基本的な手順と注意点/3.下鼻道法を安全かつ確実に行うための工夫 | |||
| XI | 直接シリコーンチューブ挿入術とDCR下鼻道法【芳賀照行】 | ||
| 1.鼻涙管が長い場合/2.いわゆるダンベル型涙嚢炎/3.下部開口が閉塞して,不明の場合 | |||
| XII | 結膜涙嚢鼻腔吻合術(Jonesチューブ留置術)【中川 喬】 | ||
| 1.手術の適応/2.術式/3.術後処置/4.合併症/5.自験例 | |||
| XIII | 新しい結膜涙嚢鼻腔吻合術(結膜2重弁法)【新田安紀芳】 | ||
| 1.結膜2重弁法の手術手技/2.術後管理/3.結膜2重弁法の特徴 | |||
| XIV | N-DCR:涙嚢鼻腔新吻合術【前川二郎・西條正城】 | ||
| 1.はじめに/2.方法/3.対象と結果/4.N-DCRと従来法との比較 | |||