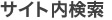‘書籍案内’ 一覧
涙嚢鼻腔吻合術と眼瞼下垂症手術 Ⅱ 眼瞼下垂症手術
2010年4月15日 木曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho057.htm涙嚢鼻腔吻合術と眼瞼下垂症手術 Ⅱ 眼瞼下垂症手術
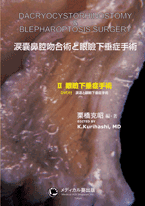 |
眼瞼下垂症手術の最新の道標!
|
|||||||
内容目次
| 1 | 総論(1) 松尾清教授のご講演より【栗橋克昭】 | ||
| 1.松尾清教授の先進性/2.挙筋腱膜とアキレス腱/3.遅筋と速筋/4.α運動ニューロンとγ運動ニューロン/5.Marcus Gunn現象/6.ミュラー筋は眼瞼挙筋のための縦列の筋紡錘/7.ミュラー筋センサーの刺激サークルと歯根膜センサーの刺激サークル/8.閉口筋歯根膜反射/9.ミュラー筋を温存する眼瞼下垂症手術/10.挙筋腱膜を固定すると同時に,開瞼のじゃまをする抵抗組織をはずす/11.再発しても瘢痕をつくらないようにすると何回でも再手術が可能/12.ミュラー筋はどの部分も切除してはならない/13.ミュラー筋近位部に局在する機械受容器と,そこから出る三叉神経固有知覚技/14.狭瞼器はミュラー筋を損傷する/15.ミュラー筋の瞼板の近くは最もsensitiveな部分で,切除してはならない/16. ミュラー筋は平滑筋で,胃の平滑筋と同じように張力をとってやると縮んでいく/17.眼瞼痙攣は腱膜性眼瞼下垂症の進行したもの/18.青斑核 | |||
| 1 | 総論(2) 眼瞼下垂症手術とその周辺【栗橋克昭】 | ||
| 1.症例/2.眼瞼下垂症手術 | |||
| 2 | 眼瞼下垂症手術の概略と基本手技【西條智博】 | ||
| 1.上眼瞼の解剖/2.眼瞼下垂症手術/3.手術中の止血操作/4.術中の切開操作 | |||
| 3 | 眼瞼下垂-私のポイント 下垂症手術をはじめる人のために【五嶋摩理】 | ||
| 1.一般的な下垂症状と手術適応の決定/2.上眼瞼の解剖/3.術式,術後経過/4.合併症/5.症例/6.眼科医として手術する | |||
| 4 | 初心者の眼瞼下垂症手術【宮久保 寛】 | ||
| 1.術前検査と説明/2.眼瞼の形状と術中所見/3.麻酔/4.皮膚切開/5.眼輪筋,隔膜の瞼板上からの剥離/6.隔膜,挙筋の同定/7.定量とtucking/8.全身との関連 | |||
| 5 | 上眼瞼の解剖【長内 一】 | ||
| 1.上眼瞼挙筋/2.挙筋腱膜/3.ミュラー筋/4.”LPS sheath”/5.瞼板,眼輪筋,皮膚/6.滑車の必要性/7.Whitnall靱帯/8.ITL/9.サンドイッチ構造/10.弾性線維でつながっているのは | |||
| 6 | 眼瞼下垂症手術の適応,術式および結果【芳賀照行】 | ||
| 1.眼瞼下垂症手術の適応/2.眼瞼下垂症手術の要点/3.手術結果 | |||
| 7 | 眼瞼下垂症手術-術式と症例報告(1)【永原 幸】 | ||
| 1.眼瞼挙筋,眼瞼の解剖と手術戦略/2.臨床における眼瞼下垂の評価方法/3.検査結果から考える手術戦略/4.周術期管理/5.症例報告(ミュラー筋のタッキング法) | |||
| 8 | 眼瞼下垂症手術-術式と症例報告(2)【河合憲司】 | ||
| 1.眼瞼下垂症手術は眼科と美容外科の狭間にあり/2.筆者が知る眼瞼下垂症手術下垂症手術に関する最近の知見の知識/3.手術法の選択/4.眼瞼 | |||
| 9 | 白内障手術医のためのミュラー筋短縮術【花崎秀敏】 | ||
| 1.手術方法/2.不定愁訴に対する治療効果 | |||
| 10 | 私が行っている術式-挙筋短縮術【黒田真一郎】 | ||
| 1.手術適応/2.私が気をつけている大きなポイント/3.私が気をつけている小さなポイント/4.麻酔/5.狭瞼器/6.止血/7.皮膚切開/8.手術手順 | |||
| 11 | 炭酸ガスレーザーを使用した眼瞼下垂症手術【宮田信之,金原久治】 | ||
| 1.手術成績/2.眼窩上神経ブロック/3.炭酸ガスレーザーによる組織切開と剥離/4.ミュラー筋タッキング/5.結果/6.考察 | |||
| 12 | 腱膜性眼瞼下垂症に対する通糸法手術【小笠原孝祐,小田島祥司】 | ||
| 1.手術の実際/2.手術のコツ/3.本術式の適応について/4.本術式の奏効機序についての考察 | |||
| 13 | 先天眼瞼下垂症【羅 錦營】 | ||
| 1.眼瞼下垂症:総論/2.眼瞼下垂症:各論 | |||
| 14 | 星状神経節照射療法の(眼科的)応用【祐森弘子】 | ||
| 1.星状神経節ブロック(SGB)/2.星状神経節ブロックの適応/3.半導体レーザーによる星状神経節近傍照射法(レーザーSGL) | |||
| 15 | 星状神経節直線偏光近赤外線照射療法(Stellate Ganglion Lizer:SGL療法)について【松崎敏男】 | ||
| 1.星状神経節ブロック(SGB)と星状神経節照射(SGL)/2.神経内科領域でのSGL療法 | |||
| 16 | 眼瞼下垂症手術と自律神経機能【嶋津和弘】 | ||
| 1.自律神経機能検査/2.負荷サーモグラフィ/3.心電図R-R間隔分析/4.症例 | |||
| 17 | 難治性円形脱毛症に直線偏光近赤外線照射が有効【岡田まゆみ】 | ||
| 1.単独またはSGBとの併用で,有効率86.3% | |||
眼形成外科-虎の巻-
2010年4月14日 水曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho059.htm眼形成外科-虎の巻-(DVD付き)
 |
眼形成外科のグローバル・スタンダードを紹介 世界の最新情報がこの一冊に!
品切れ |
|||||||
眼形成外科に関する教科書は今までに数多く出版されてきましたが,それらの教科書を丹念に紐解いてみると,何十 年も内容が変わっていないことにお気づきでしょう.雑誌で眼形成外科に関して特集が組まれることがありますが,引用文献の大半が日本語の論文や教科書であ ることが多く,そこでは欧文文献からの知識の輸入すらされず,古い知識が長年循環してきました.また,本邦からの眼形成外科に関する論文投稿数は長きにわ たり,非常に低いレベルで推移してきました.
このような現状のため,本邦の眼形成外科に関しては“鎖国”同然の状態が数十年続いており,欧米ではすでにstandardの地位を確立している術式が,未だ,本邦では知られていないことが多くあります.
眼形成外科は“外眼部”といわれ,“眼球”を専門とする眼科医から一段低くみられてきたことは否めません.それは,本邦からの欧文雑誌への投稿が,眼形 成外科では他分野に比べて著しく少なかったことが原因の一つかもしれません.また,大半の医局に眼形成外科を専門とする医師がいなかったことも一因かもし れません.
一方,世界に眼を向けてみると,眼形成外科も他分野同様,日進月歩で進歩しています.
このような現状を鑑み,欧米ではすでにstandardとなっている術式や最新の眼形成外科を紹介する目的で本書を執筆しました.大部分は,私の出版し てきた論文を加筆訂正したもので,そのなかでは,欧米でgold standardとなっている内容がほとんど網羅されています.ただし,理解の容易のため,本書では外来でよく遭遇し,処置が必要となる疾患,すなわち, 一般眼科医が手術可能な疾患に限定しました.写真をふんだんに取り入れ,DVDも付けましたので,本書だけで手術をマスターすることは十分に可能です.本 書が先生方の日常診療の一助となり,広く患者が益することができることを望みます.
(序文より)
内容目次
| I | 眼形成外科の基本手技 | ||
| 1.はじめに/2.Atraumatic technique/3.麻酔方法/4.メス刃と切開方法/5.止血/6.持針器・剪刀の持ち方/7.縫合法/8.曲剪刀の扱い方/9.デザイン/10.写真撮影法 | |||
| II | 上眼瞼下垂(概論,Levator Resection) | ||
| 1.はじめに/2.上眼瞼の解剖学的特徴/3.上眼瞼下垂の程度分類/4.Aponeurotic ptosis診断のポイント/5.手術適応と治療方針の決定/6.手術禁忌と適応にあたっての注意事項(A.眼球運動障害/B.外傷性眼瞼下垂/C.若年者/D.高齢者/E.ドライアイ患者/F.Murcus-Gunn現象(Jaw-Winking)/7.使用器械/8.手術手技(Levator complexの固定と術中定量/重瞼の作製/縫合)/9.術後処置/10.合併症とその対策(A.血腫/B.過矯正/C.低矯正/D.ドライアイ) | |||
| III | 上眼瞼下垂(吊り上げ術) | ||
| 1.はじめに/2.適応/3.吊り上げ材/4.手術/5.術後処置/6.合併症など(A.低矯正/B.眼瞼おくれ/C.吊り上げ材の脱出,霰粒腫様の肉芽腫形成) | |||
| IV | 下眼瞼内反症 | ||
| 1.はじめに/2.下眼瞼の解剖/3.分類/4.発祥病態(A.退行性下眼瞼内反症/B.瘢痕性下眼瞼内反症/C.睫毛内反症)/5.診察,治療法(A.退行性下眼瞼内反症に対する診察,治療法/B.睫毛内反症に対する診察,治療法)/6.術後処置 | |||
| V | 睫毛乱生 | ||
| 1.はじめに/2.発症病態/3.術前診察/4.手術方法(A.睫毛根電気分解/B.瞼縁の楔形切除,縫縮/C.切開法重瞼術を応用して瞼縁を回転させる方法/D.Lid splitting with lash resection(Wojno変法)/5.術後処置 | |||
| VI | 眉毛下上眼瞼リフト・上眼瞼形成術 | ||
| 1.はじめに/2.上眼瞼皮膚弛緩症/3.眉毛下上眼瞼リフトの手術/4.上眼瞼形成術/5.術後処置 | |||
| VII | 眉毛下垂症 | ||
| 1.はじめに/2.眉毛の正常位置/3.眼瞼下垂やその他の偽眼瞼下垂との鑑別/4.手術/5.術後処置/6.合併症とその対策/7.再発 | |||
| VIII | 霰粒腫 | ||
| 1.はじめに/2.霰粒腫の成因および臨床・病理所見(A.霰粒腫の成因/B.霰粒腫の臨床所見/C.鑑別診断/D.病理所見)/3.霰粒腫の治療(A.保存的療法/B.ステロイド局所注射/C.切開掻爬)/4.術後処置 | |||
| IX | 下眼瞼外反症 | ||
| 1.はじめに/2.下眼瞼外反症の原因/3.検査と手術適応/4.Kuhnt-Szymanowski Smith変法/5.Lateral tarsalstrip procedure/6.術後処置 | |||
| X | 眼窩脂肪ヘルニア | ||
| 1.はじめに/2.眼窩脂肪ヘルニアとは/3.眼窩脂肪ヘルニアの手術に対する誤解/4.眼窩脂肪ヘルニアの手術/5.術後処置 | |||
| XI | 先天鼻涙管閉塞 | ||
| 1.はじめに/2.総論/3.診断(A.先天鼻涙管閉塞の診断B.鑑別診断/C.通水試験について)/4.治療(A.先天鼻涙管閉塞における自然治癒について/B.Probingを行う時期について-諸外国とわが国での相違/C.全身麻酔か点眼麻酔か/D.保存的治療の実際/E.Probingについて/F.Probingのコツ)/5.おわりに | |||
| XII | 手術用(治療用)説明書 | ||
| XIII | 眼形成外科用語英和辞典 | ||
中心性漿液性脈絡網膜症
2010年4月14日 水曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/sho058.htm中心性漿液性脈絡網膜症 Central Serous Chorioretinopathy:CSC
 |
CSCに関する国内外の1,000件を超える文献をあますところなく紹介した多年の集大成!
|
|||||||
中心性漿液性脈絡網膜症(central serous chorioretinopathy:CSC)は,現在使用されている正式な病名である.1866年von Graefeが“Central rezidivierende Retinitis”の病名で発表して以来,今日まで実に多くの病名が使用されてきた.その理由は本疾患の原因がはっきりしていないからである.本症は網 膜と脈絡膜の疾患であり,現在は病因の主座は脈絡膜にあると考えられている.網膜の障害は2次的に起こるとされており,脈絡網膜症 (chorioretinopathy)が使用されている所以である.しかし,なお原因は不明であり,さまざまなrisk factorが指摘されている.
中心性漿液性脈絡網膜症は1965年に蛍光眼底造影検査が開発される以前には,黄斑病変や中心暗点をきたす種々の疾患の一部が,いわゆる“中心性網膜 炎”として報告されてきた可能性を否定できない.また,適切な治療法もなかったのである.蛍光眼底造影検査と光凝固治療が1960年代後半から発展し,本 症の診断が確立され,治療手段も発展した.
本書は,1965年以降今日まで発表された約1,000件を超える論文を,ほぼ年代順に記載し,中心性漿液性脈絡網膜症の診断と治療が過去約50年間に いかに発展してきたかを総覧したものである.本疾患は網脈絡膜のみの疾患ではなく,全身疾患との関連が今日まで報告された論文から多く読みとることができ る.本書が臨床にたずさわる諸兄の今後の研究の参考になれば幸甚である.
(序文より)
内容目次
| I | 病因・病理・統計 | ||
| 1.病名と病因論(病名/病因論)/2.疫学・統計(疫学/統計)/3.病理組織/4.病因(脈絡膜循環障害/精神心因的状態とCSC/カテコールアミン) | |||
| II | 臨床所見 | ||
| 1.視力/2.自然経過,長期経過/3.色覚/4.視野と網膜感度/5.電気生理/6.網膜色素上皮剥離と黄斑外色素上皮萎縮巣/7.多発性後極部網膜色素上皮症,胞状網膜剥離,異型中心性脈絡網膜症,急性色素上皮炎 | |||
| III | 検査 | ||
| 1.蛍光眼底造影(法)/2.走査レーザー検眼鏡(SLO)/3.インドシアニングリーン蛍光眼底造影(法)/4.光干渉断層計(OCT)/5.眼底自発蛍光 | |||
| IV | 合併症,鑑別 | ||
| 1.合併症,鑑別/2.ステロイド/3.妊娠 | |||
| V | 治療 | ||
| 1.薬物/2.光凝固(西独キセノン光凝固/東独キセノン光凝固)/3.レーザー光凝固(ルビーレーザー/アルゴンレーザー/クリプトンレーザー/Nd-YAGレーザー/色素レーザー/マイクロパルスダイオードレーザー)/4.再発/5.光線力学治療(PDT) | |||
| VI | 総説・解説 | ||
書籍案内
2010年4月14日 水曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/book.htm書籍一覧
別途、送料が一律500円かかります。お買い上げ金額10,000円(税別)以上で送料無料。
書評
2010年4月13日 火曜日 https://www.medical-aoi.co.jp/book/shohyo.htm網膜静脈閉塞症
 |
|
|
網膜静脈閉塞症は眼底出血の代表であるが、これを総合的に扱ったモノグラフが刊行された。
著者の戸張は、本症の急性期に光凝固が著効を奏することを世界で初めて報告した。東大眼科にいた昭和46年(1971)のことであり、それ以来、約4,000例の治療経験がある権威である。
網膜静脈閉塞症は単一疾患ではない。網膜静脈分枝閉塞症BRVOと網膜中心静脈閉塞症CRVOの、発症機序と予後が大きく異なる2疾患からなっているからである。この本でも、両者の違いに十分配慮しながら論述が進められている。
本書は8つの章からなる。疫学と統計、発生機序と病理、分類、自然経過、臨床所見、合併症、検査、治療がそれである。
ページ数の配分からみると、最後の「治療」がもっとも詳しい。どの項目にも内外の文献がしっかり引用され、さらに、ほとんどのページにカラーや蛍光眼底造影の写真が提示されているので、学問的であると同時に、図譜としての性格を合わせて持っている。
網膜静脈閉塞症は頻度の多い疾患なので、とかく「なんでも知っている」という気になりがちであるが、本書をみていくと、思いがけない新知見が随所に出てくる。
BRVOは網膜の動静脈交叉部の血管閉塞、そしてCRVOは網膜中心静脈の閉塞と単純に考えられやすい。「8.臨床所見」の章にある「血液」の項目は、血液の粘稠度や赤血球の変形能、さらには血管内皮増殖因子VEGFなどの異常が素因としてある可能性を示している。
BRVO・CRVOでは、そ の発症初期の所見は良く知られているが、陳旧化した場合や合併症については知見が乏しい。前者では網膜裂孔と硝子体出血、そ して後者では緑内障が大きな問題である。それらについても本書の記述は親切であり、臨床家にとっても有用な情報を提供している。 「治療」の章では、著者らが創始した光凝固はもちろん十分に解説されているが、それ以外の方法についての記述も詳しい。血栓を溶解させる線溶療法、ダイア モックス(R)とプロスタグランジン、硝子体手術、レーザーを使った網膜と脈絡膜間の静脈吻合術、さらには最新の手術法である交叉部での膜切開術sheathotomyまで扱われている。
モノグラフといえば、「なんでも書いてあるが堅苦しい本」と思われやすい。ところが本書は、文献をしっかり引用して学問的でありながら、「臨床家のための実戦的な本」という性格が強く出ている。
文章は平易である。一気に通読することができるが、「網膜静脈閉塞症がこれだけ幅と奥行きの深い疾患であるのか」という印象を強く受けた。本書が広く読まれ、その内容が眼科医すべての常識となることが願われるのである。
「日本の眼科」 Vol.74(2003年) No.3 より
著者の戸張は、本症の急性期に光凝固が著効を奏することを世界で初めて報告した。東大眼科にいた昭和46年(1971)のことであり、それ以来、約4,000例の治療経験がある権威である。
網膜静脈閉塞症は単一疾患ではない。網膜静脈分枝閉塞症BRVOと網膜中心静脈閉塞症CRVOの、発症機序と予後が大きく異なる2疾患からなっているからである。この本でも、両者の違いに十分配慮しながら論述が進められている。
本書は8つの章からなる。疫学と統計、発生機序と病理、分類、自然経過、臨床所見、合併症、検査、治療がそれである。
ページ数の配分からみると、最後の「治療」がもっとも詳しい。どの項目にも内外の文献がしっかり引用され、さらに、ほとんどのページにカラーや蛍光眼底造影の写真が提示されているので、学問的であると同時に、図譜としての性格を合わせて持っている。
網膜静脈閉塞症は頻度の多い疾患なので、とかく「なんでも知っている」という気になりがちであるが、本書をみていくと、思いがけない新知見が随所に出てくる。
BRVOは網膜の動静脈交叉部の血管閉塞、そしてCRVOは網膜中心静脈の閉塞と単純に考えられやすい。「8.臨床所見」の章にある「血液」の項目は、血液の粘稠度や赤血球の変形能、さらには血管内皮増殖因子VEGFなどの異常が素因としてある可能性を示している。
BRVO・CRVOでは、その発症初期の所見は良く知られているが、陳旧化した場合や合併症については知見が乏しい。前者では網膜裂孔と硝子体出血、そ して後者では緑内障が大きな問題である。それらについても本書の記述は親切であり、臨床家にとっても有用な情報を提供している。 「治療」の章では、著者らが創始した光凝固はもちろん十分に解説されているが、それ以外の方法についての記述も詳しい。血栓を溶解させる線溶療法、ダイア モックス(R)とプロスタグランジン、硝子体手術、レーザーを使った網膜と脈絡膜間の静脈吻合術、さらには最新の手術法である交叉部での膜切開術sheathotomyまで扱われている。
モノグラフといえば、「なんでも書いてあるが堅苦しい本」と思われやすい。ところが本書は、文献をしっかり引用して学問的でありながら、「臨床家のための実戦的な本」という性格が強く出ている。
文章は平易である。一気に通読することができるが、「網膜静脈閉塞症がこれだけ幅と奥行きの深い疾患であるのか」という印象を強く受けた。本書が広く読まれ、その内容が眼科医すべての常識となることが願われるのである。
「日本の眼科」 Vol.74(2003年) No.3 より